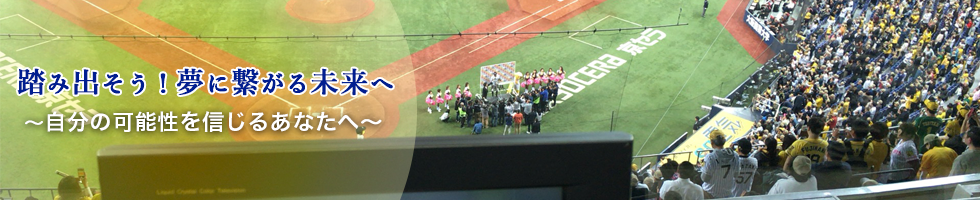11月13日受講生ブログ
今週の講座では原稿読みを行いました。改めて「声に出して伝わる読み方」の難しさを感じました。講座で使用した原稿には専門的な用語も多くありました。専門的な原稿になればなるほど、固有名詞であったり、レース名であったり分からない単語が増えます。よほどアナウンスの技量があれば別でしょうが、理解できていないと漢字の読み間違いや、言葉を変な位置で区切ってしまったり、文章の流れを切ってしまったりします。それでは原稿の本来の意味を伝えられません。
伝えるためには、まず調べます。声に出すことからは一度離れるので、一見すると遠回りに見えるかもしれません。ですが私たちは「原稿の言葉」を伝えるためにアナウンスしているわけではなく、「原稿の意味」を伝えるためにアナウンスしています。意味の分からない内容は伝えようがありません。そのために調べるのです。調べると徐々に言葉の意味が分かり始め、原稿が伝えたい意味が見えてきます。そこから全体の構成を考え、どこが大事になるのかを考え、段落ごとや間の取り方などを工夫していきます。ここまでしてようやく「声に出して伝わる読み方」になります。
伝えるための工程を書き起こすと、大変に見えるかもしれません。ですが、日常生活では当たり前のように行えていることなのです。
「今日は晴れていて気持ちがいいですね」なんてことない日常会話です。ですが、相手に伝えるために意味を理解しながら、その時の状況に合わせた抑揚で言葉を発します。普段から「言葉の意味を理解する」「適切な音の抑揚がある」などしっかりできているのです。ただ、原稿になると自分の言葉ではなく、人の言葉になるので難しく感じるのかもしれません。
しかし原稿読みは基礎工事、他のことにも通じます。声を出すインタビューや実況にもつながっていきます。そして、原稿に登場した知らない言葉は調べることで知識として蓄積されていきます。声に出す部分は技術として身についていきます。知識と技術、両方を兼ね備える原稿読みは改めて素晴らしいなと感じました。
2025年11月21日 05:08